小学1年生の頃の思い出話です。
プチトマトを巡る高橋との争い。僕が流した涙の訳とは。
小学校入学
小学校1年生の頃の僕は、今よりもずっとずっと純粋な少年だった。
初めての学校生活。引っ越してきた新しい土地。とにかく見るものすべてが新しかった。
学校生活はすぐに慣れ、友達も簡単に出来た。
悩みもなく、疲れもなく、とにかく毎日が輝いていたあの日。
僕はプチトマトと出会った。
プチトマト
小学校に入るまで、僕が食べることが出来ないほどトマトが嫌いだった。
特にトマトの中でも味の濃いプチトマトは、嫌いな食べ物ランキングの最上位にランクインされていた。
そんなプチトマトを学校で栽培することが決まったとき、僕はかなり絶望したのを覚えている。
どうしてわざわざ毎日水をやってまで、嫌いなプチトマトを育てなければいけないのか。
輝いていたはずの学校生活に、もやもやと暗雲が立ち込め始めたのを感じた。
「プチトマト育てるなんてめんどっちー」
「そもそもトマト美味しくないよな」
僕はそんな話を友人の高橋(仮名)としたりしていた。
愛着
嫌々していたプチトマトの栽培。
しかし、これが意外と面白かった。
プチトマトの種はすぐに芽を出し、そしてすくすくと成長していった。
世話をすれば世話をするほど、成長を見せてくれるプチトマト。
愛着を感じないわけがない。
その頃から、僕は自宅でプチトマトを食べるようになり始めた。
プチトマトも意外とまずくない。
そんな風にも思い始めた。
そして次第に増してくるのが、自分が育ってたプチトマトを収穫するときの期待感である。
僕の育てたプチトマトはどんな味がするのだろう。
お店で買うトマトよりも美味しいのだろうか。不味いのだろうか。
そんなことを色々と考えながら、あっという間に月日は流れていった。
収穫
そして迎えた収穫日。
僕の育てたプチトマトは、見事綺麗な赤い実を実らせていた。
この日、僕はわくわくしながらプチトマトを収穫したのを覚えている。
僕は収穫したプチトマトを透明な袋に入れ、そして手にギュッと握りしめた。
僕の心のわくわくがピークを迎える。
このとき既に、今日の晩飯のサラダには、僕が育てたプチトマトがトッピングされることが決まっていたのだ。
ドレッシングには何をかけよう。
僕の育てたプチトマトは美味しいだろうか。
両親は喜んでくれるだろうか。
プチトマトのことを考え過ぎて、この後の授業はあまり集中できなかった。
そして最後の終わりの会でも、僕はまるで上の空の状態だった。
ランドセルに教科書を詰めて帰る準備万端の状態にし、机の上に置いたプチトマトをぼんやりと眺めていた。
ぼんやりしたまま終わりの会が終わる。
そして僕が帰ろうとしたとき、事件は突然発生した。
高橋
本当に一瞬の出来事だった。
「はい、どーん!」
突然高橋の声と共に、目の前に黒いランドセルが現れた。
どうやら高橋がふざけながら、ランドセルを僕の机に叩きつけたらしい。
高橋によるふざけた脅かし。
普段の僕なら、笑って受け流すことが出来る。
このときも、いつものように受け流そうとしていた。
しかし、このとき気が付いてしまった。
高橋のランドセルは、明確にあるものを標的としていた。
そして今確実に、高橋のランドセルの下にはあるものが下敷きになっている……。
この事実に気が付いたとき、途端に僕の視界がうるうるとぼやけ始めた。
そしてランドセルに潰されたあるものを確認したとき、僕はとうとうこらえきれなくなった。
「ぼ、僕のプチトマトがーーー!!」
あとにも先にも、僕が他人の前で涙を流したのはこれが最初で最後である。
感じる無力感
透明な袋の中でぐちゃぐちゃになったプチトマト。
もはや僕のプチトマトは、プチトマトとしての原型をとどめていなかった。
「うぐっ……うぐっ……」
必死に涙をこらえようとする僕。
泣き顔を見られないように机に突っ伏したが、次第に教室がざわつき始めた。
「先生! 高橋くんがまつようじくんを泣かしました!」
ご丁寧に、わざわざ大声で先生に報告する女子。
「まつようじくん大丈夫?」
心配してくれる優しい女子。しかし、慰めの言葉は僕を余計辛くさせる。
慰められたところで、もう僕のプチトマトは返ってこない。
怒りに任せて高橋に反撃するという手段もあったが、僕は相変わらず机に伏せたままだった。
仕返しに高橋のことを殴りたかったが、勝てる気がしないので止めた。
何も出来ない弱い自分、守れなかったプチトマト……。
僕は何とも言えない自分の無力感に打ちのめされた。
先生のフォロー
しばらくして、僕の元に担任の先生が現れた。
ベテランのおばちゃん教師だ。
「まつようじくんどうしたの?」
優しく僕に問いかける先生。しかし僕は机に伏せたままだった。
僕の態度を見て質問を諦めたのか、今度はクラスの女子に状況を尋ねる先生。
そして一通り状況を把握した先生は、高橋と僕以外を家に帰らせ、そして高橋に軽く説教した。
その間も、僕は机に顔を伏せたままだった。
なんだかもう顔を上げるタイミングを失っていた。
「まつようじくん、いい加減顔を上げなさい」
先生に注意され、僕はようやく顔を上げる。
そこから先生は、僕に色々と言い始めた。
「高橋に悪気はなかった。だから彼を許してあげて欲しい」
先生は確かそんなことを言っていた気がする。
まあこのときもう既に、僕は高橋に対する怒りの感情はなくなっていた。
プチトマトを守れなかった僕が悪い。
そんな風に考えられるくらい、小1の割りに僕の精神年齢は高かった。
そして僕は、高橋と仲直りの握手をした。
違う、そうじゃない
プチトマトが潰されてからわずか10分ほど。
事件は早くも解決に向かおうとしていた。
短時間で状況を把握し、僕と高橋の関係修復まで果たしたおばちゃん教師の実力の高さが伺える。
しかし今振り返って考えてみても、この後の最後の先生の言葉だけは、どうしても納得することができない。
その言葉は、僕と高橋が帰ろうとするときに先生の口から発せられた。
「高橋くん、仲直りの印に、まつようじくんにあなたのプチトマトを分けてあげたら? まつようじくんも、大好きなプチトマトが食べられたら満足でしょう?」
あまりに咄嗟のことで、僕は何も言い返せなかった。
そして僕は先生に言われるまま、高橋のプチトマトを持って帰ってしまった。
あのとき僕が言いたかったのに言えなかった言葉。
それを今、この場を使って声を大にして言いたい。
「先生! 僕はべつに、プチトマトが食べられなくて泣いたわけじゃねえよ! 自分が育てたプチトマトが潰されたから泣いたんだよ! 別に高橋の育てたプチトマト食べたところで何にも嬉しくねえよ! ……そもそもプチトマトなんて嫌いだよ! 大嫌いだよ! 嫌いな高橋の嫌いなプチトマト持って家に帰る僕の気持ち考えろよ! めちゃくちゃ惨めだよ!」
それから
それから僕は家に帰り、母親に高橋のプチトマトを差し出した。
高橋に自分の育てたプチトマトを潰されたこと。
このプチトマトは高橋のプチトマトだということ。
結局何も言えなかった。
夕飯のサラダ。
予定通りトッピングされるプチトマト。
しかしそのプチトマトは僕が育てたのではない。高橋が育てたのだ。
両親は美味い美味いと言いながら高橋のプチトマトを食べた。
そんな両親を悲しませないように、僕も美味い美味いと高橋のプチトマトを食べた。
このとき僕は、目から再び涙を流した。
この涙の本当の理由を、たぶん僕以外は誰も知らない。
追記
このとき初めて、僕は人に気持ちを伝えることの難しさを感じた気がする。
そしてそれと同時に、思いやりが他人を傷つけることもあるということも、プチトマト事件は僕に教えてくれた気がする。
慰めてくれた女子も、
助けてくれた先生も、
美味しいと言ってくれた両親も、
あの頃の僕にとっては全てが辛いことだった。
あとそれと、あのとき食べた高橋のプチトマト……
クソまずかった
つづく
タグ:ねくおた誕生記
画像:© 魔法少女まどか☆マギカ

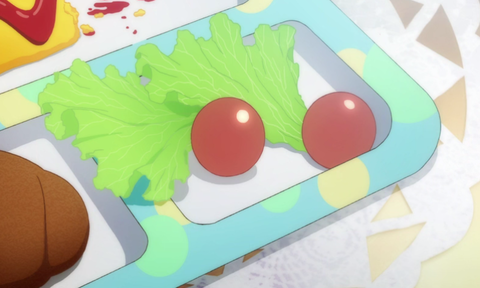









コメント